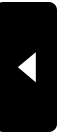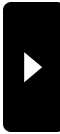ここまで来ると、やらなければならないことや、考えるべきことがたくさんあることが判って、段々憂鬱な気持ちになってきたかもしれませんね。全てを自社でやるとなると、ちょっと大変だな・・そう思った時に、考えてほしいのが保育事業者への委託です。
どんな業界でも同じですが、大手と言われる会社と、そうでない会社が存在します。
やっぱり大手さんは安心だよね・・・たいていの人は単純にそう思うのかもしれません。
例えば、物販や製造、飲食業の会社でしたら、企業にはスケールメリットが発生し、消費者にも安価で物が手に入るという利点が発生します。そして、誰でも物が作れるように、誰でも商品が売れるように、その手法をマニュアル化できます。
しかし、事業所内保育施設はどうでしょうか?
土地も違う、預かるお子さまも違う、会社の業態も違う、保育士の採用状況も違う、施設の作りも違う、そして、設置者の目的や思いも違う・・。正直、同じ施設などありません。
だから、それぞれの設置者の意向や状況にあわせて、ひとつひとつのアイディアを積み上げたオリジナルの施設運営が求められます。もちろん、運営書類等の流用はできます。
しかし、先ほど挙げたような根本な〝違い〟をマニュアル化することは非常に難しい事業です。何ヵ所運営させて頂いても検討事項は違うし、頭を悩ませる問題は常に発生する、保育現場は実にアナログなのです。設置者の風土も様々ですしね。その都度、相談や話し合いを重ねて、より良い方法を探っていくことが必要となります。
そして、運営する内容が細かい。緊急性が問われる事態が発生することもあります。
当社も、先生方から判断を仰ぐ連絡が毎日入ってきます。
どんな業界でも同じですが、大手と言われる会社と、そうでない会社が存在します。
やっぱり大手さんは安心だよね・・・たいていの人は単純にそう思うのかもしれません。
例えば、物販や製造、飲食業の会社でしたら、企業にはスケールメリットが発生し、消費者にも安価で物が手に入るという利点が発生します。そして、誰でも物が作れるように、誰でも商品が売れるように、その手法をマニュアル化できます。
しかし、事業所内保育施設はどうでしょうか?
土地も違う、預かるお子さまも違う、会社の業態も違う、保育士の採用状況も違う、施設の作りも違う、そして、設置者の目的や思いも違う・・。正直、同じ施設などありません。
だから、それぞれの設置者の意向や状況にあわせて、ひとつひとつのアイディアを積み上げたオリジナルの施設運営が求められます。もちろん、運営書類等の流用はできます。
しかし、先ほど挙げたような根本な〝違い〟をマニュアル化することは非常に難しい事業です。何ヵ所運営させて頂いても検討事項は違うし、頭を悩ませる問題は常に発生する、保育現場は実にアナログなのです。設置者の風土も様々ですしね。その都度、相談や話し合いを重ねて、より良い方法を探っていくことが必要となります。
そして、運営する内容が細かい。緊急性が問われる事態が発生することもあります。
当社も、先生方から判断を仰ぐ連絡が毎日入ってきます。
例えば、お子さまの増員による翌日の保育士配置、お子さまのけがの処置判断、食物アレルギーの疑いの症状についての見解、お子さまの発達に関わる判断、行政からのFAXやTELの内容報告と対応など、事務処理的なことから、保育に関すること、〝今〟判断してほしいという子ども達の命に関わるようなことまで、内容も幅広い。
当たり前のことですが、「請負」という契約形態は、指揮命令権が請負業者、つまりこの場合だと保育事業者にあります。先生方が困った時に、しっかりと適切な指示を出してあげなければなりません。場合によっては、すぐに駆けつけることも必要でしょう。
このようなことを考えると、この事業に関しては、フットワークがよく、柔軟な対応ができる地元の保育事業者を選択するのが良いのではないかと思います。地元の病院情報にも明るく、行政の担当者ともつながりがあることも運営上のメリットのひとつとなるでしょう。
加えて、考えて頂きたいことがあります。
このようなことを考えると、この事業に関しては、フットワークがよく、柔軟な対応ができる地元の保育事業者を選択するのが良いのではないかと思います。地元の病院情報にも明るく、行政の担当者ともつながりがあることも運営上のメリットのひとつとなるでしょう。
加えて、考えて頂きたいことがあります。
「施設を運営する」ことと、「保育を知っている、保育ができる」ことは違うということです。
資料によると、施設運営の課題として「保育の質の管理・維持 13.5%」が挙げられています。
資料によると、施設運営の課題として「保育の質の管理・維持 13.5%」が挙げられています。
(経済産業省 平成21年度サービス産業生産性向上支援調査事業(事業所内保育施設等実態調査事業)報告書による)
特に、保育事業者に委託している従業員301人以上の企業になりますと、23.7%もの企業が、保育の質に何らかの課題を感じているというデータが出ているのです。
保育の現場を知らない人が先生方を管理しようとすれば、数値上、書面上のみの効率重視の運営になりがちです。
こんな例があります。
保育の現場を知らない人が先生方を管理しようとすれば、数値上、書面上のみの効率重視の運営になりがちです。
こんな例があります。
直営で運営していたある事業所内保育施設を請け負った保育事業者は、経費を削減するために、保育士の人数を減らし、給料を極端に下げました。
それゆえ、直営時に働いていた保育士は殆ど退職し、新体制で運営スタート。
しかし、結局保育士が安定せず、入れ替えを繰り返すことになったのです。
保育士の定着が悪ければ、保育の内容を検討するどころではありません。
引継ぎ不足、統一感のない対応の連続で、日々の業務そのものが危うい状態に陥ります。
それは当然保護者にも伝わり、結果として40名近くいたお子さまが、保育事業者の運営開始6ヶ月後には10名以下にまで落ち込んでしまったのです。
もちろんある程度の効率性は必要ですが、現場ありきの運営をしていかなければ、保育の質を高め、維持していくという課題を克服することは難しいと私は考えます。
例えば、保育士の配置。1・2歳児6名に対して保育士が1名という基準があったとしても、この時期のお子さまの個体差は非常に大きいものがあります。1歳になったばかりの子が6名と、もうすぐ2歳になろうとしている子の6名は大きく違うということです。
お預かりするお子さまの月齢の成長を正確に判断し、保育士2名ではお子さまの安全が保たれないと思えば、そこに1名の保育士をフリーとして加える、私ならそう判断します。
しかし一方、基準どおりにできないのは保育士の力量不足だと判断する保育事業者もあります。そうすると先生方は目の前のことに追われ、毎日を何事もなく過ごすことが目的となります。
引継ぎ不足、統一感のない対応の連続で、日々の業務そのものが危うい状態に陥ります。
それは当然保護者にも伝わり、結果として40名近くいたお子さまが、保育事業者の運営開始6ヶ月後には10名以下にまで落ち込んでしまったのです。
もちろんある程度の効率性は必要ですが、現場ありきの運営をしていかなければ、保育の質を高め、維持していくという課題を克服することは難しいと私は考えます。
例えば、保育士の配置。1・2歳児6名に対して保育士が1名という基準があったとしても、この時期のお子さまの個体差は非常に大きいものがあります。1歳になったばかりの子が6名と、もうすぐ2歳になろうとしている子の6名は大きく違うということです。
お預かりするお子さまの月齢の成長を正確に判断し、保育士2名ではお子さまの安全が保たれないと思えば、そこに1名の保育士をフリーとして加える、私ならそう判断します。
しかし一方、基準どおりにできないのは保育士の力量不足だと判断する保育事業者もあります。そうすると先生方は目の前のことに追われ、毎日を何事もなく過ごすことが目的となります。
子ども達がケガをしないように、外で遊ばせることもなくお部屋の中で静かに過ごす、おむつ替えも、トイレトレーニングもままならない、食事も楽しんで食べることを教えるのではなく、ただ口に詰め込んで食べさせるということになってしまうわけです。
例えば、時に広汎性発達障害(自閉症など)などが見られるお子さまもいたりします。
当社が運営するある施設でも、そのような疑いのあるお子さまがいたことがあります。
幼稚園の入園を控え、先生方にも焦りがあり、対応に苦慮していました。
例えば、時に広汎性発達障害(自閉症など)などが見られるお子さまもいたりします。
当社が運営するある施設でも、そのような疑いのあるお子さまがいたことがあります。
幼稚園の入園を控え、先生方にも焦りがあり、対応に苦慮していました。
小さなお子さまだけに判断が難しいのです。
先生方から相談を受けて、何回か施設内でのお子さまの様子を観察し、確かに不安だと感じて、しかるべき相談機関を手配して巡回指導に来て頂きました。そのため、発達状況の把握と、表れの考え方、保育士としての適切な対応を教えて頂き、先生方の気持ちも救われたのです。
先生方は小さなお子さまの大事な命を預かっています。何ごとも早期発見が大事。
ちょっとおかしい、なんとなく変だ、という先生方の経験による『感』は侮れません。
先生方からの申し出を、タイミング良く拾い上げて対応することは、やはり保育を知る事業者でないとできないことだと思いますね。
しかし、設置者の皆さまが、保育事業者が保育に明るいか否かを判断するのは非常に難しいことです。保育の力を計る方法は色々ありますが、保育士配置の考え方と安全対策(防災、アレルギー、不審者対応、感染症など)が最も解りやすい目安になるのではないかと私は思います。
皆さまの質問に対し、明確な根拠を示して複数の提案ができるか?よく精査してみて下さい。
先生方から相談を受けて、何回か施設内でのお子さまの様子を観察し、確かに不安だと感じて、しかるべき相談機関を手配して巡回指導に来て頂きました。そのため、発達状況の把握と、表れの考え方、保育士としての適切な対応を教えて頂き、先生方の気持ちも救われたのです。
先生方は小さなお子さまの大事な命を預かっています。何ごとも早期発見が大事。
ちょっとおかしい、なんとなく変だ、という先生方の経験による『感』は侮れません。
先生方からの申し出を、タイミング良く拾い上げて対応することは、やはり保育を知る事業者でないとできないことだと思いますね。
しかし、設置者の皆さまが、保育事業者が保育に明るいか否かを判断するのは非常に難しいことです。保育の力を計る方法は色々ありますが、保育士配置の考え方と安全対策(防災、アレルギー、不審者対応、感染症など)が最も解りやすい目安になるのではないかと私は思います。
皆さまの質問に対し、明確な根拠を示して複数の提案ができるか?よく精査してみて下さい。
考え方の根底に子ども達の命を守る意識があれば、それは信用していいのではないでしょうか。
それと、もうひとつ。
設置者と請負業者との円滑なコミュニケーションの大切さを挙げておきましょう。
私はほぼ毎日、設置者の担当者とメールや電話で話をしています。
それと、もうひとつ。
設置者と請負業者との円滑なコミュニケーションの大切さを挙げておきましょう。
私はほぼ毎日、設置者の担当者とメールや電話で話をしています。
お子さまの様子はもちろん、気になった保護者の様子も情報提供としてお話しますし、場合によっては保護者の配属先の責任者の方とも、話をすることもあります。先生方の意向を踏まえた提案もし、色々な相談も受けながら、解決に向けてお互いが行うことを確認したりします。
保育事業者は保育の専門家ですので、物事の視点を、どうしても〝お子さまにとってどうなのか?〟ということに置きます。
一方、設置者には設置者には事業所内保育施設を開設した目的があります。
採用対策、雇用の安定、福利厚生が主目的だったとしても、そこに少しでも「子育て支援」の意識を持っていただけると、コミュニケーションがスムーズになるのではないかと思います。
設置者、運営者、そして保護者。みんなで従業員のお子さまを育てる感覚・・ですね。
例えば、育休明けにいきなりフルタイムでお仕事を始めるのは、預けられるお子さまにとっては非常に負担になります。そうであれば、復職前に少しでも慣らし保育をしておくとか、それが叶わなければ復職時の勤務時間を段階的に伸ばして頂くとか。サービス業であれば、お子さまが落ち着くまでは、規則正しい日程や、同じ時間にシフトを組んでいただくなど。
また、保育環境においても、設置者としてのイメージを優先してしまうと、お子さまの安全や心地よい生活が損なわれるともあったりするのです。
そのあたりのことを私達がご相談した時に、設置者の方々が多少なりともご理解していただけると大変有り難いですね。子ども達が事業所内保育施設に毎日喜んで行ってくれるようになれば、保護者である皆さまの従業員は、より安心してお仕事に励めることでしょう。
保育事業者は保育の専門家ですので、物事の視点を、どうしても〝お子さまにとってどうなのか?〟ということに置きます。
一方、設置者には設置者には事業所内保育施設を開設した目的があります。
採用対策、雇用の安定、福利厚生が主目的だったとしても、そこに少しでも「子育て支援」の意識を持っていただけると、コミュニケーションがスムーズになるのではないかと思います。
設置者、運営者、そして保護者。みんなで従業員のお子さまを育てる感覚・・ですね。
例えば、育休明けにいきなりフルタイムでお仕事を始めるのは、預けられるお子さまにとっては非常に負担になります。そうであれば、復職前に少しでも慣らし保育をしておくとか、それが叶わなければ復職時の勤務時間を段階的に伸ばして頂くとか。サービス業であれば、お子さまが落ち着くまでは、規則正しい日程や、同じ時間にシフトを組んでいただくなど。
また、保育環境においても、設置者としてのイメージを優先してしまうと、お子さまの安全や心地よい生活が損なわれるともあったりするのです。
そのあたりのことを私達がご相談した時に、設置者の方々が多少なりともご理解していただけると大変有り難いですね。子ども達が事業所内保育施設に毎日喜んで行ってくれるようになれば、保護者である皆さまの従業員は、より安心してお仕事に励めることでしょう。